岐阜あるあるカルタ「YAONE」にちなんだ岐阜愛エッセイの連載企画も、ようやく「さ行」。今回は「水」と「緑」にまつわる岐阜の特性から派生した多面的な”岐阜あるある”が揃っています。
【あるあるエッセイ「あ」~「お」はコチラ】
【あるあるエッセイ「か」~「こ」はコチラ】
さ 最強無敵! 天にそびえる 岐阜城天守

お城といえばどこにあるイメージですか?――岐阜でこんな質問をしたら、おそらく多くの方が「そりゃあ山の上が普通やないの?」と、答えるはず。なんせ我らが誇る岐阜城は、天守が標高329m(東京タワーとほぼ同じ高さ)と、遥か頭上にそびえる天空の城!その城下で暮らす生粋の岐阜人にとって、「ラスボスの最終拠点は山上の砦が相場」というのは、刷り込みレベルの常識なわけです。

でも他県民から見たらこの姿は驚くべき城の在り方らしく…。実際私も学生時代、東京から来た友人にその事実を突きつけられる出来事がありました。それは観光案内も兼ねてバスで岐阜のまちを周遊していたときのこと。岐阜公園の横を通過する際、突然友人が「ちょ…ありえないんだけど!!」と、素っ頓狂な声を上げたのです。「え、何が?」と、こちらもビックリだったのですが、聞けば「あんな行くだけでも大変そうな山(=金華山)のてっぺんにお城があるなんて狂気じみてる」ということだそうで。何もそんな言い方しなくても…と内心複雑に思いながらも、当たり前と思っていた山上の岐阜城天守が実は規格外の存在であることに気づかされた瞬間でもありました。
ふと自分を振り返ってみると、確かに他県でお城(=主にまちなかの平城)観光に行く度、「あれ?お城なのに山の上にないんや」と幼心に不思議に思っていた記憶。もちろん子どもの頃は自分の常識の方がマイノリティーだと気付けるはずもなく、「こんなまちなかにお城造ったら危険やおね?金華山みたいな山があればよかったのに」なんて、優越感含みで余計な心配までしていた気がします。
そんなこともあって、岐阜城の型破りなビジュアルついては二十歳前後で客観視できるようになったつもりだったのですが、その異様な威容をまざまざと感じるようになったのは近年のこと。例えばここ数年、岐阜市の代名詞ともなっている「月と岐阜城」。望遠レンズでとらえた巨大な月と天守をとらえた、月が地球に大接近しているような写真は、さすがは第六天魔王・信長公の城と言いたくなる圧倒的な迫力です。

また、雨上がりに靄がかった岐阜城もなかなか乙。特に峻険な山のてっぺん、天守付近が雲海で見え隠れしている姿は得体のしれない伏魔殿といった風情で、眺めているだけでゾクゾクドキドキします。


季節でいえば、個人的には初夏が大好き。山じゅうのツブラジイが咲き乱れて山全体が黄金色に染まる様子は、さすがはド派手な信長様のおわす場所(ニオイもすごいんですけど)!山事態が黄金なんて、これはもうチート級のビジュアルですよね。

一方で山上に至れば、眼下に広がるのはまさに天下布武の絶景。遠く伊勢湾の地平線まで見渡せる濃尾平野は、夜になればまち灯りの絨毯に包まれます。

このドラマチックな景色も、岐阜城がまちのど真ん中にあればこそ。こんな大都会(敢えて言います!)の頭上に聳える摩天楼の如き山城こそ、まさに「最強無敵」の称号がふさわしいと思いませんか?
だから目をつぶってほしいのです、岐阜城が過去に4度も落城しているという史実には…。
し 蛇口から 出る水うまい 清流味

のどが渇いたとき、お薬を飲むとき、コーヒーやお茶を淹れるとき――きっと多くの方が日々の生活のあらゆるシーンで水道水を口にしているのではないでしょうか。個人的に特に飲みまくった時代は小学生の頃。夏の日の体育の授業の後に飲む水のうまさといったらもうこの上なく…!!上向きにした蛇口を全開にひねって、のどをゴキュゴキュ鳴らしながら浴びるほど水を飲んだ記憶のある方、きっと多いのではないでしょうか。私の通っていた小学校では、「1番左の蛇口が一番冷たい」とか「3番目の蛇口の水がおいしい」とか「5番目の蛇口の水は、トイレの水だから飲まない方がいい」なんてガセネタまで、水道水に関するゴシップはいつもクラス中に流布していたように思います。

前置きが長くなりましたが、何が言いたいかというと、岐阜の水道水はものすごく美味だということ。
とはいえ日々の暮らしの中で、水の味を意識することってあまりないのでピンとこないかもしれません。でも例えばこんな経験はありませんか?県外に出かけて飲食店でお水を飲んだ時、「あれ?水ってこんな味だったっけ…」と疑問に思ったこと。旅行先の宿の水道で歯みがきしたとき、「ん、なんだろうこのニオイ」と感じたこと。そう、岐阜人にとっておいしい水は、空気と同じくらい当たり前の存在。だから他地域で水を口にしたとき、岐阜の水がいかに美味であったかにようやく気付かされるのです。聞くところによると岐阜の水に惚れてこの地に移り住む料理人さんも、けっこういらっしゃるそうですよ。めちゃくちゃ嬉しい話ですよね!
事実、岐阜の水は名実共に超優秀。下記に「長良川(中流域)」の水の輝かしい栄光についてざっと紹介してみると、
・名水百選(環境省/昭和60年)
・名水百選選抜総選挙「おいしさがすばらしい名水部門」で全国5位
・「水道水がのおいしい都市」32都市に選抜(厚生省「おいしい水研究会」昭和60年)
――何が驚きって岐阜市はけっこうな都市部であるにもかかわらず、とにかく水が「おいしい」とお墨付きをいただいていること。おいしい水の水質要件として、ミネラル含有量、硬度、臭気や残留塩素等様々な項目があるのですが、岐阜の水はいずれもこれをクリア(ここでは鏡岩水源地)。データで見てもその水質は折り紙付きなのです。
ちなみに岐阜市の水道水の水源は「長良川の伏流水(川底のさらに下へ浸透した水)」と「地下水」。川やダムを利用せず自然の力で濾過した水は、浅井戸からくみ上げた時点でミネラルウォーター級!そのためここに微量の消毒液を加えて紫外線処理を行うのみで、各家庭に配水することができるのです。そう聞くと、岐阜の水がおいしい理由も納得ですよね。

日本の真ん中、岐阜の都市を流れる一級河川でありながら、本流にダムや大工場群がなく美しい清流を保つ長良川の水。水そのものがおいしいのはもちろん、清流の女王・鮎を育み、古来鵜飼の舞台になるなど(※「う」の札参照)岐阜の文化と暮らしは、豊かな美しい水と共に育まれてきたものであるといえます。
蛇口をひねれば名水が出てくる幸せは、岐阜の宝。その尊さに感謝しながら、目覚めの一杯、お茶にコーヒー、毎日大切に味わいたいものです。
す 全ての道は 橋に通ずる 岐阜の地理
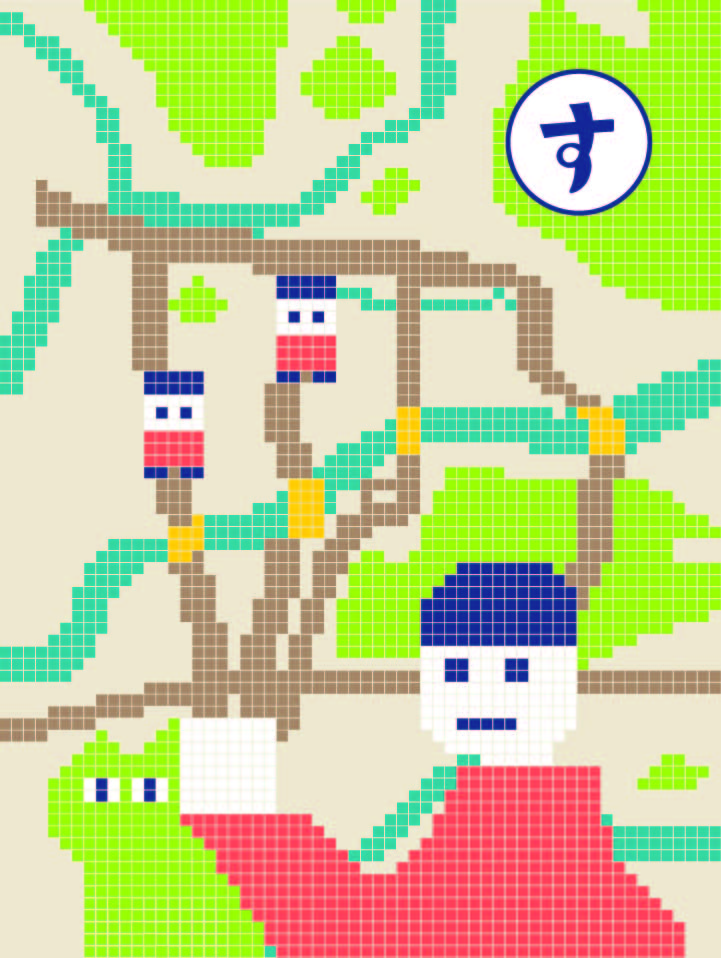
「し」の札では、「長良川」の“水”と私たちの暮らしの密接な関わりについてご紹介しましたが、「す」でフィーチャーするのは、“地理”の面においても、長良川をはじめとする川が、岐阜人の感覚にしみついているというお話。
例えばYAONEを販売してくださっている本屋さん「カルコス本店」への行き方を誰かに伝えるとき、皆さんはどんな風に説明するでしょうか。
「鏡島大橋を川北に行って、大縄場大橋の道を右折やね」
「島大橋を真っ直ぐ東に行くと、大縄場大橋の手前で右手に見えてくるで」
「環状線をず~っと南に行くやろ。そしたら鏡島大橋の手前の大きい通りで左折やわ」
といった感じで、どちらの方面から向かうにしても橋基準で道を伝えるシーンが多々あるはず。個人差はありますが、車社会なことも影響してか岐阜人は駅やバス停よりも川と最寄りの橋で位置関係を把握している方が、とっても多いような気がします。

そもそも大きく東西に長良川が横切る岐阜市では、ざっくりと「川北」と「川南」という分け方で地理を把握するし、長良川に関していえば藍川、千鳥、鵜飼いに長良、金華、忠節、大縄場、鏡島、(長良川橋梁)、河渡、穂積大橋…と、上流から順に橋の名前をすらすら唱えられる方も少なくないでしょう。特に、岐阜市の中心市街地においては東(上流)から「長良橋通り」、「金華橋通り」、「忠節橋通り」と、長良川の橋の名を冠する通りが南北に走っているのも見逃せないポイント。「長良川と橋」は岐阜市の地理把握の基準であり、中枢を担う存在ともいえるのです。YAONEの地図(※ぜひパズルを完成させてみてください)を見ても、その様子は一目瞭然ですよね。
ちなみに長良川は緩やかに蛇行しているので、「河渡橋と鏡島大橋」、「鏡島大橋と大縄場大橋」のように道の延長線上でクロスし合うことも。こうした関係性を頭に入れ、川と橋を脳内地図の中心軸に据えることで、市内の大まかな位置関係と道筋は、ほぼほぼ把握することができます。
ただこの地理の覚え方、おそらく岐阜人独特のものなので、初めて岐阜に来た方は困惑するかも?確かに道を尋ねても説明の主なポイントが「川を越えるか越えないか」と「どの橋を通るか」だけだったら、岐阜の地理を知らないとちんぷんかんぷんですよね、そりゃあ…。
そんな岐阜人には、暮らすエリアや世代によって長良川に架かる橋への思い入れがあったりするもの。個人的にも忠節橋と金華山のコラボレーションは、やっぱりいつ見てもいいなあと思うし、大縄場大橋ができたとき(1991年竣工)の記憶は今も鮮明。橋に上がるときの1回転ループが近未来の建造物みたいに見えて「めちゃくちゃカッコイイ~」と、当時大興奮したことは今も忘れられません。そんな思い出が今も残っているせいか、大縄場大橋は今もついつい意識的に選んで渡ることが多い気がします。こういう好み(=推し橋)に加えて時間帯や渋滞具合によって瞬時に橋をチョイスできるようになったら、もうかなりの橋上級者ですよね。

橋を制する者は岐阜市の地理を制す!!
必ずどこかの橋に通じている全ての道を使いこなすことができれば、岐阜人レベルもグンと格上げされる…かもしれません。
せ 贅沢と 知らずに食べる 給食の鮎

夏が近づいてくるとスーパーや魚屋さんの店頭にも並び始める鮎は、食べる風物詩。「今年ももうそんな時期なんやねぇ」と、まだ小ぶりの若鮎を天ぷらや南蛮漬けで丸ごと頬張る初夏、いよいよ成熟してきた鮎を塩焼きでかぶりつく夏の盛り、卵をたっぷりはらんだ子持ちの落ち鮎に舌鼓を打つ秋…。折々に魅力的な鮎と共に初夏~晩秋にかけての季節の機微を感じるのも、なかなか乙な食体験です。ヤナに行って鮎をフルコースでたらふくいただくのも、年に1度はしたいプチ贅沢ですよね。


このように鮎は、岐阜人にとって比較的身近で日常的に親しまれてきた魚の一つ。語弊があるかもしれませんが、鮎に対して鮭の切り身やイワシと並んで日々の食卓のレパートリーになるような、庶民的なイメージを持っている方もけっこういるかもしれません。だから2015年に鮎が世界農業遺産に認定されたときや、都会の高級料亭で超高値取引されていると知ったときに「へぇ~」と驚いた経験のある方、実は多いのではないでしょうか。
なぜなら岐阜で子ども時代を過ごした岐阜人たちは、給食の一皿として鮎をごく当たり前に食してきたわけですから。私が子どもの頃は、まあまあの頻度で皿食器(一番浅くて大きい容器)のメイン料理として、「鮎の甘露煮」が登場していた記憶。ちなみに私はこの料理を地味メニュー寄りにカテゴライズしていたので、「わぁ、今日は鮎の甘露煮だ~♡」なんてテンションを上げることもなく、甘辛いほろほろの身を黙々と口に運びながら「これは米飯が進む系の味だな」とか「うむ、骨まで全部食べられるな」などと極めてフラットな状態で、その美味を堪能していたような気がします。

今思えばもっとありがたがって食べればよかったなと思うのですが、ハンバーグとか唐揚げと違って、控えめな佇まいでお皿にいた鮎の甘露煮は、その美味しさとは裏腹に目立たない存在だったんですよね。最近の岐阜の給食では「アユの薬味だれ」なんていう米粉をまぶして揚げた鮎に、爽やかな薬味ソースをかけたなんとも洒落たメニューもあるようなので、機会があれば食してみたいなと思っています。絶対おいしいですよね、これ。
閑話休題、結論として言いたいのは岐阜の鮎が高級であろうと庶民的であろうと地味であろうと、とびきり美味なのはまごうことなき事実ということ。そしてこの当たり前に享受していた美味が、世界に認められるほどすごい価値のあるものであるということ。さらっとすごい話だなあと感心せずにはいられません。
長良川を拠点に漁業が営まれ、水を守るための森・川の保全活動と、水を巡る伝統的な暮らしがある――そんな里川における連鎖は「長良川システム」と呼ばれ、今も大切に守り伝えられているもの。古来岐阜で長きにわたり育まれてきたこうした岐阜の暮らしや文化は、長良川の鵜飼(うの札)や、水の素晴らしさ(しの札)にも繋がる岐阜の宝なのです。
清流の偉大さに感謝し、その賜物である鮎を食す。小中学生の皆さんは給食の鮎、ぜひ大切に味わってくださいね。
そ そろそろ夕餉 でも食べちゃうの 五平餅
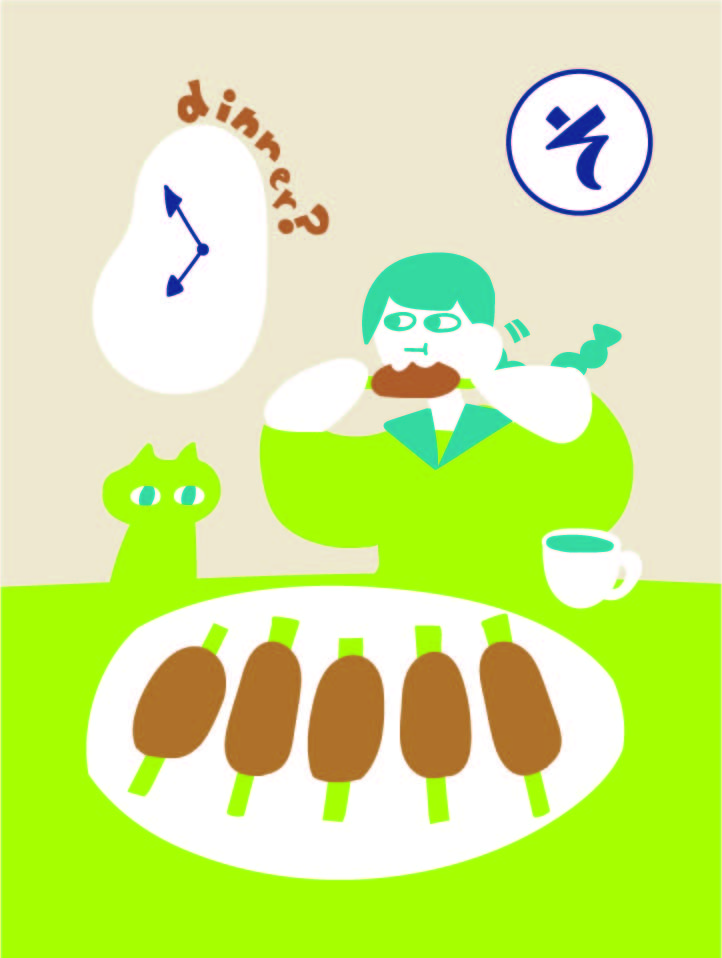
観光地の食べ歩きの花形として、はたまたサービスエリアや道の駅の屋台メニューとして、絶対的人気を誇る串グルメ「五平餅」。でも近年、「あれ、五平餅って全国区の食べ物じゃなかったんや…」と、岐阜人が地味に衝撃を受けた二つの出来事、皆さんはご存じでしょうか?

一つは映画「君の名は。」で、飛騨の旅路の最中に司くんと奥寺先輩が五平餅を食べたときのこと(2016年)。そしてもう一つは岐阜(東濃)が舞台になった朝の連続テレビ小説「半分、青い。」で、秋風羽織先生が五平餅を大絶賛したときのこと(2018年)。どちらの作品でも魅力的に登場していたので、私も五平餅欲が普段よりかな~り高まっていたものです…。が、この二つの出来事がトリガーとなった空前絶後の五平餅ブームには、正直なところ驚愕しました。なんせ五平餅を買うためにできた長蛇の列を見たのは、人生初。五平餅は昔からどこにでもあるお馴染みの屋台グルメという感覚だったので、県外の観光客がそれに殺到するという図が、にわかには信じられませんでした。それまで五平餅は、みたらしだんご同様(※これもどうやら一概には言えなさそうですが、いずれまた「を」の項で)、どこでも買える串グルメと思っていただけに、久々のカルチャーショックだったのです。
ちなみに私がよく五平餅を買うのは、スーパーや道の駅の売店。大抵みたらしだんごやその他のおやつ、軽食と並んで売られていて、あの香ばしい匂いについつい誘惑されてしまいます。特に小腹がすいた夕方前の葛藤は、人生でも指折りに悩むひとととき。「腹具合でいえば今すぐ五平餅にかぶりつきたい。しかしここで五平餅を食べては夕飯に差し障る。ここは大人しくだんごにとどめておくのが賢明だろうか。いや、やはりここは本能に従って五平餅を…」――そんな風にコンマ数秒頭の中で逡巡した後、結局はかなりの確率で五平餅を選ぶことが多い気がします。タレの焦げる匂いテロの威力には、並の精神力ではなかなか太刀打ちできないんですよね(笑)。ただ五平餅ってみたらしだんごと比べると食べ応えも圧倒的。東濃地方にはお漬物やおかずと一緒に定食として出しているお店もあるくらいのボリュームなので、小腹満たしのつもりでいると思った以上の満足感。夜に焼肉食べ放題とか、フレンチのフルコースの予定がある場合は注意が必要です。
さて、一口に「五平餅」といっても、地方によって味も形も違うのが興味深いところ。醤油や味噌、クルミダレ…などなどその味わいも地域によって千差万別です。例えば飛騨の五平餅は、えごま(あぶらえ)がたっぷりのタレが欠かせません。

このギュギュッと滋味が凝縮した味がクセになって、飛騨に行くとお醤油のだんごと並んで食べたくなるんですよね。また、個人的には東濃地方によくある、「おだんご型」の五平餅もお気に入り。五平餅の主流である「わらじ型(※「君の名は。」と「半分、青い。」の五平餅はどちらもこれ)」とは一線を画すこの形状は口の周りを汚さずパクパク食べやすい上、タレとお焦げがまんべんなくあるのも嬉しいポイントです。

こういう五平餅が、中山道の馬籠宿と妻籠宿を結ぶ峠の茶屋にあったりするのがまたいいんですよねぇ。江戸時代の旅人風情を楽しみながら舌鼓を打つのもちょっぴり粋な五平餅の食し方だなあと思います。
お出かけしたら、岐阜県各所の五平餅を食べ比べてみるのも一興。五平餅というシンプルなグルメ一つで個性豊かかつ多様な岐阜の食文化が垣間見えるのは、なかなか面白いですよ。


